先に書いた「評価方法」を使用して移動運用用アンテナを製作しました。
今回は、この評価方法の部分について焦点をあてつつこのアンテナを紹介します。
この当時、移動運用用としてブーム長4.3mの4エレYagi-Udaを使用していましたが、これは他の局と比べると少し小さめのアンテナでした。他の局との競争力を高めるため、大きくても良いからゲインのあるアンテナが欲しくて製作しました。ブーム長は7.8mほどになります。
設計にはYOというパソコンソフトを使用しています。ゲインを優先させ、帯域とF/Rを少し犠牲にしました。
以下にその寸法を示します。(YOの表記方法を採用)
| Position | Length | |||
| 25 | 12 | 10 | ||
| Ref | 0 | 45 | 455 | 1000 |
| DE | 620 | 45 | 455 | 895 |
| Dir 1 | 2005 | 45 | 455 | 885 |
| DIr 2 | 3995 | 45 | 455 | 860 |
| Dir 3 | 6025 | 45 | 455 | 853 |
| Dir 4 | 7760 | 45 | 455 | 850 |
エレメントの位置、径、長さ
(エレメント中心部が太いのはエレメントブラケットを考慮してのもの)
マッチング条件は以下の通り
| Rod Diameter | 10.0mm |
| Rod Spacing | 125.0 |
| Rod Length | 165.0 |
| DE Length | 1373.0 |
| Lead Length | 20.0 |
| Series Cap | 99999.0pF |
| Feed Z | 200Ω |
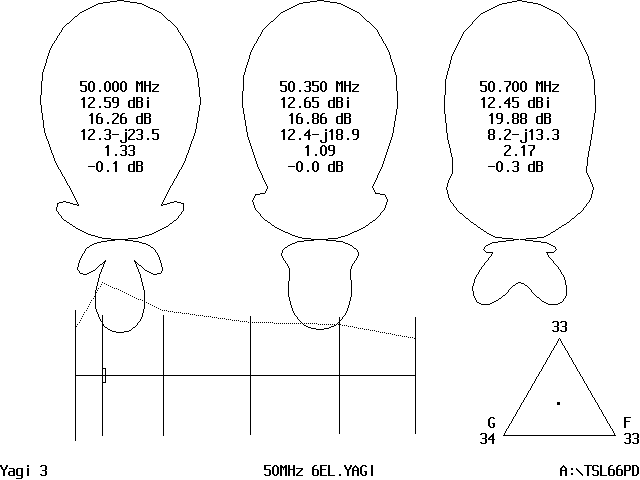
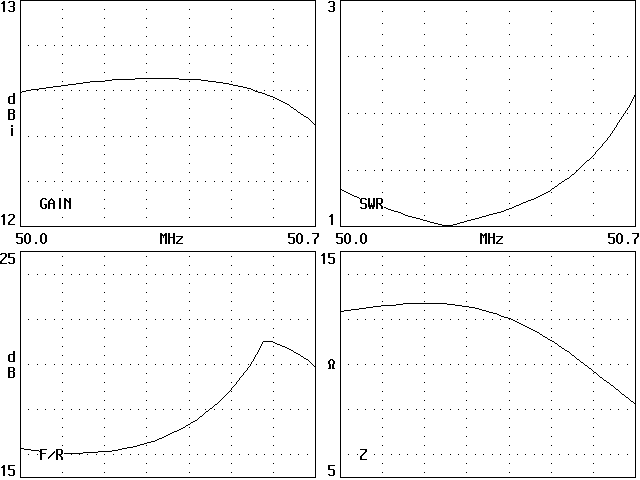
上記アンテナを製作してみました。 まずは、YOの結果どおりに組み立てます。
 |
| 製作中のアンテナ 安倍川の河川敷にボール盤という異様な光景(hi) |
そして、SWRの測定をします。マッチングはTマッチ+Uバランとしました。給電部の様子は以下のようになっています。
 |
| 給電部の様子 |
マッチングはYOの結果どおりにしても希望のSWR特性が得られなかったので、少々調整をしました。
Tマッチの場合は、エレメントの長さと、クリップの位置を変化させて調整します。
調整の結果、以下の条件にした時にSWRの特性がほぼ希望通りになりました。
| Rod Diameter | 10.0mm |
| Rod Spacing | 125.0 |
| Rod Length | 200.0 |
| DE Length | 1417.0 |
| Lead Length | 20.0 |
| Series Cap | 99999.0pF |
| Feed Z | 200Ω |
この時のSWR特性を、解析結果と実測とで比べてみます。(7mhでの結果)
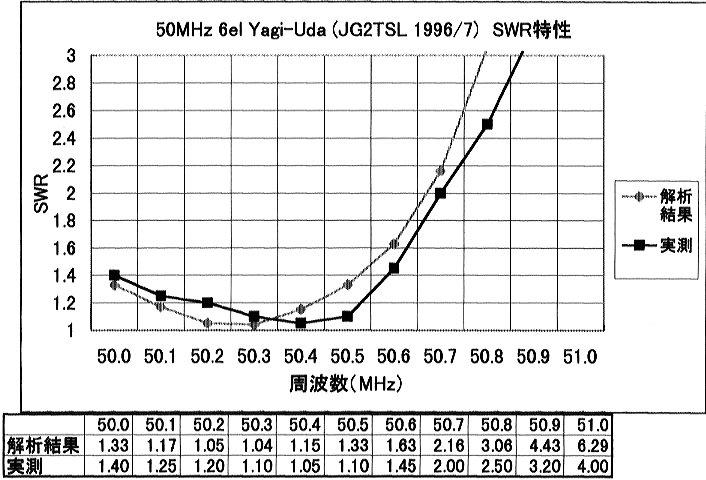
SWRボトムの周波数は少しずれましたが、ほぼ同じようなSWR特性が得られています。
でも、SWRだけでは本当に解析通りに実際のアンテナが出来ているかは少し疑問があります。そこで、「F/Bvs周波数」のグラフの比較を行ってみました。以下がその結果です。

この測定をした後、実際に手でグラフを書いてみたときの驚きはかなりのものでした。
YOの解析結果とほぼ同じ結果が実測結果として出てしまったのですから!
周波数的なずれは100KHzくらいしかないと思われます。
ここまで一気に結論を書いてしまいましたが、ここで以上の実測時の設備を紹介しておきます。

|
| 送信側のアンテナの様子(HB9CV) (人物は実験に協力していただいたJI2XPB) |

|
| 送信機の様子 FT-690で0.5Wで送信 |

|
| これが今回製作したアンテナ ちなみに実験場所は清水市駒越海岸です。 送信アンテナとは80mほどの距離があります。 |

|
| 測定装置 IC-551にステップATTを付けただけです。 送信側からの電波を受信する。 551のSメーターが同じように振れるように ステップATTを調整し、F/Bを測定する。 |
以上のように、アンテナシミュレーターを使用してのアンテナの製作も、SWRの測定だけでなく、F/B比の測定を行うことで、その性能がより正確に確認することができたと思います。この後、1年ほど移動運用でこのアンテナを使用しました。良く飛びましたよ〜。
でも、この1年後に、このアンテナは改造してしまうことになります。それはまた続きで書きます。
以上の過程で、製作にはJL2HIW良知さんに、実測にはJI2XPB内野さんに協力していただきました。どうもありがとうございました。
ご意見、ご感想はこちらまで→jg2tsl@jarl.com