1997年の「6m静岡県珍市珍郡一斉移動」の富士郡芝川町移動のために製作した5エレ
Yagi-Udaアンテナについて解説したいと思います。この年の芝川町移動では、「担ぎ上げ」を行った為、これに対応するためのアンテナを製作する必要がありました。そして誕生したのがこのアンテナです。このアンテナを「ver.
Tenshi」(バージョン テンシ)と勝手に命名しました。「Tenshi」は担ぎ上げを行った山の名前「天子ケ岳」(てんしがだけ)から拝借しました。
まずは、今回製作したアンテナに要求された条件を整理してみます。
これは担ぎ上げの為に要求される条件です。
軽さを得るためにエレメント、ブーム、どちらも細くすることで対応しました。
運搬時の長さですが、あまり多くの箇所で継ぎ足しくないので、エレメント2分割を限度としました。最も長いエレメント、リフレクターを2分割した時の長さ1.5m以下にすることにします。1.5mという長さは、担ぎ上げ移動の長さとしては少々長すぎるようです。しかし、マストも縮めた時の長さが2m近くになってしまうので気にしないことにしました。運搬性はあまりよくないでしょう。でも、担ぎ上げは不可能ではありません。
「移動用アンテナ」として様々な組立の方法が試されています。
「目玉クリップ式」は、移動用アンテナの組立方法として普及しており、組立、撤収の容易さでは非常に優れた方法です。しかし、重さの面と、壊れやすさの面で少し問題があるように思います。自分も以前は目玉クリップ式のアンテナを移動運用で使用していましたが、目玉クリップからエレメントが外れて、「天からエレメントが降ってきた」ことを何度も体験しています。その為にアンテナを上げ直さなければならないのならまだしも、道路脇で運用していて、通行の車に当たりそうになった時はヒヤッとしました。
今回の移動では、担ぎ上げと言えども、RTTYを運用しました。RTTYの周波数は、50.9MHz〜51.0MHzで、この周波数でも低SWRとする必要があります。その上にはFMの周波数帯がありますが、メインチャンネルである51.0MHzにごく近いところだけSWRが落ちていれば良しとします。
ハイゲインだけを追求すれば、もう少し良いデザインがあるかもしれませんが、1MHzもの帯域を持たせると、少々のゲイン低下はやむを得ないと割り切りました。それでも、ブーム長から考えられる極限のゲインよりも0.5dB程度しか落ちないようです。F/Bについてですが、山の上はノイズ源が少ないだろうと勝手に解釈し、あまり深追いはしないことにしました。
これら本質的なアンテナの性能のチューニングにはYO(ヤギオプチマイザー)を活用します。YOは自分が使ったアンテナ解析ソフトの中では、その使用感と再現性が最も良かったからです。
条件を元に、実際のアンテナの構想を練ることにします。
まず、運搬時の長さを1.5mとしたことから、自ずとブーム長が決定されます。ブームを3本継ぎにした場合、1.5x3=4.5。3本のうち、真ん中に当たるパイプを一回り太くし、両側を細くします。すると、ただ差し込むだけで組立ができるので機構的にも簡単です。ただ、重なり部があるので、これを1ケ所辺り5cmと見積もります。最終的なブーム長は4.5-0.01-0.01=4.4mに決定します。実際は、エレメントをブームの端部に固定することができないので、端部からの余裕が必要です。これを20mmずつと見積もると、4.4-0.02-0.02=4.36m。これがRefからDir3までの距離になります。
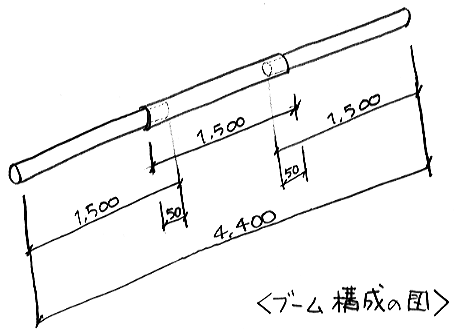
このくらいの長さのブーム長のアンテナはすでに数本作ったことがあります。前作はこのブームで4エレとしたのですが、ゲインは取れても帯域が取れませんでした。そこで、今回は5エレとしました。エレメントが増えた分、重くなりますが、ここは帯域の方を優先しました。この辺りの解説を別にまとめましたので、下記をクリックしてご覧下さい。
ブーム長とエレメント本数の違いがフロントゲインに与える影響(5エレに決定した理由)
ここまで決定したら、アンテナシミュレーターの登場です。いろいろといじり回し、大体のデザインが決定しました。帯域を広くするためには、ラジエーター付近のエレメント同士の距離を狭くすると良いようです。まずは、決定したデザインの寸法を以下に示します。YOの表記方法を採用。
| Position | Length | ||||
| 19 | 16 | 8 | 6 | ||
| Ref | 0 | 0 | 8 | 22 | 1453 |
| DE | 530 | 0 | 8 | 22 | 1363 |
| Dir 1 | 1320 | 0 | 8 | 22 | 1358 |
| DIr 2 | 2740 | 9.5 | 0 | 20.5 | 1340 |
| Dir 3 | 4360 | 0 | 8 | 22 | 1298 |
これだけでは少し分かりにくいので、以下に図で書いてみます。
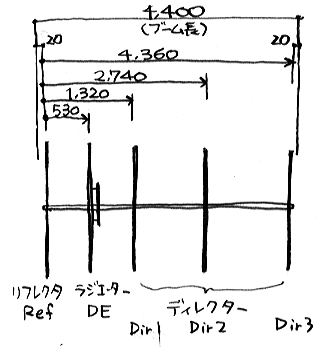
|
| <エレメントの位置> |
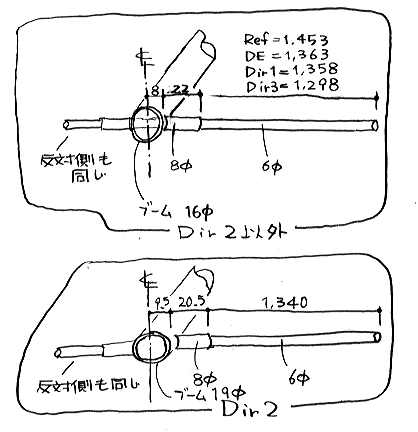
|
| <エレメントの寸法> |
上記のデザインの場合のYOの解析結果は以下の通りです。
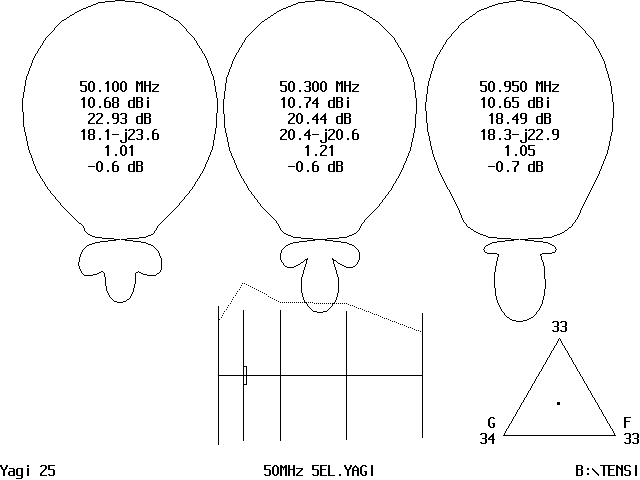 |
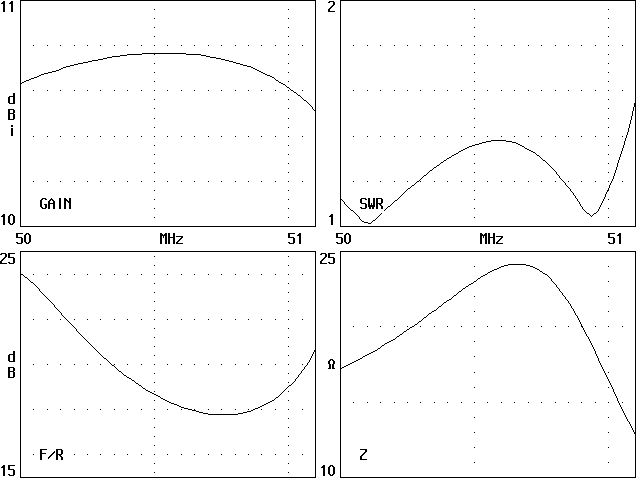 |
| フロントゲインは少し低めだが、50〜51MHzの1MHzに渡ってSWR<1.5になった。 特に、SSBとRTTYの周波数でSWRが低い。 ビームパターンは比較的きれい。 ちなみに、帯域を少し狭くなるようにラジエーターを調整すると、 50.5MHz付近のSWRはさらに改善される。 |
次に給電方法について説明します。今回は「Uバラン+Tマッチ方式」を採用しました。
Uバランとは、同軸ケーブルを1/4λ(電気長)の長さにしたものを使用し、逆相を得ることで「平衡−不平衡」の変換を行うものです。市販のアンテナでは、クリエートデザインのベストセラーCL6DXで使用されています。このバランは動作が確実で、製作も容易です。コア等を使わないため、ロスも少なそうです。ただ、インピーダンスが1:4で変換されてしまいます。
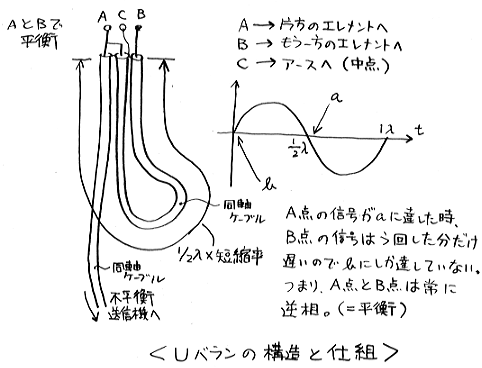
Uバランには「バラン」の役割(平衡ー不平衡の変換)しか期待していませんので、インピーダンスの変換はTマッチに任せることにします。
Tマッチは市販のアンテナでは移動用アンテナの定番F9FTで使用されています。下の図のような構造になっています。
 |
| <Tマッチの構造> |
TマッチによってSWRの調整を行うわけですが、SWR=1.0にするための条件は、R+j=50+0にすることです(送信機の出力インピーダンスが50Ωの場合)
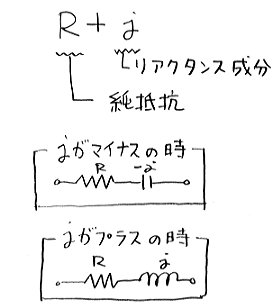 |
| SWR=1.0にする為には・・・ R(純抵抗)=50Ω j(リアクタンス成分)=0 にする。 |
単にSWRを下げると言っても、Rとj、2つの要素を調整しなければならないことになります。つまり、2ヶ所以上調整する箇所がなくてはなりません。今回のTマッチでは、上の図のl'(Tマッチの接続点の中心からの距離)とL(エレメントの長さ)の2ヶ所を調整することになります。
では、l'とLを動かすとどのようにR+jが変化するのでしょうか?
まずはL(=エレメントの長さ)から解説します。AOでダイポールアンテナの長さを変えた時のRとjの変化をグラフにプロットしてみました。
周波数は50.3MHz、エレメントは8mmのアルミパイプとします。
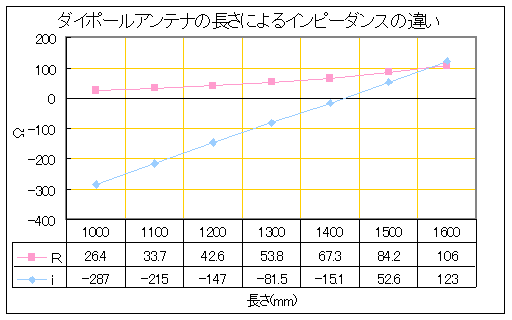
|
|
リアクタンス・・・エレメント長が短いときには容量性で、長くなると誘導性になる。 |
次にl'(=Tマッチの中心から接続点までの距離)がインピーダンスに及ぼす影響について実験してみることにしました。本当はAOで簡単に済ませたかったのですが、AOではうまく解析できませんでした。仕方が無いので、今回製作したアンテナで実測してみました。実測にはFCZ研究所のインピーダンスブリッジを使用しました。目盛りは自分で校正して振ったものですが、SWRの値と比べるとどうもずれているようです。ただ、傾向を知るには十分でしょう。結果をグラフにプロットしてみます。安倍川の土手で、5mhにver.TENSHIを設置して実測したデータです。周波数は50.3MHz。
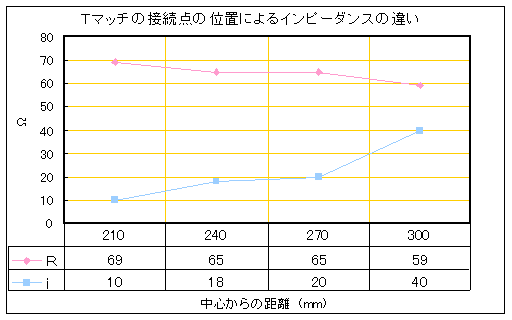 |
| 純抵抗・・・外側にずらすほど小さくなる。 リアクタンス・・・外側にずらすほど誘導性が強くなる。 |
※Tマッチはフォールデッドダイポールの変形だと思っていたので、「Tマッチの接続点の中心からの距離が大きくなるほど純抵抗が大きくなると思っていたのですが、逆の結果が実験で出てきました。予想外の結果だったのです。
以上のことから・・・
純抵抗を大きくしたい時は、Tマッチの接続点を内側にずらすか、エレメントの長さを長くする。
純抵抗を小さくした時は、Tマッチの接続点を外側にずらすか、エレメントの長さを短くする。
リアクタンスが誘導性の時は、Tマッチの接続点を内側にずらすか、エレメントの長さを短くする。
リアクタンスが容量性の時は、Tマッチの接続点を外側にずらすか、エレメントの長さを長くする。
ということになります。エレメントの長さの調整とTマッチの接続点の調整では純抵抗とリアクタンスの挙動が逆になるので、この2ヶ所を調整すれば最終的にはR+j=50+0にすることができるということです。
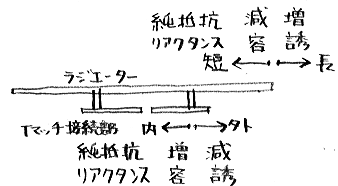
注:この部分の記述には誤りがあります! 調整編も必ず見てください!
他の給電方法を採用しなかった理由も書いてみます。
ガンママッチは本来平衡給電しなければならないエレメントに無理矢理不平衡に給電しているように自分には思えるので採用しませんでした。この方式ではインピーダンスマッチングは行っていますが、「平衡−不平衡」の変換は行っていないのです。AOのサンプルファイルでもその動作が確認できます、電流分布の図を載せておきます。
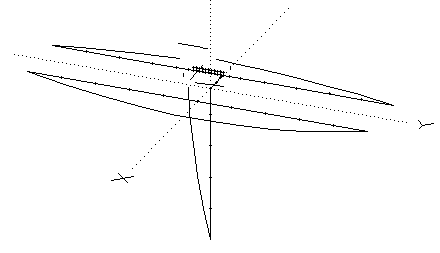
|
| ガンママッチヤギのマストに高周波電流が流れている様子。 |
平衡給電のインピーダンスマッチング方法としてポピュラーなものにヘアピンマッチがあります。クリエートやミニマルチアンテナで採用されているおなじみの方法です。しかし、この方法ではブームとエレメントを絶縁しなければなりません。この部分の機構に良い方法が思いつかなかった為、今回は見送りました。でも、本当にがっちり固定したい場合には適した方法なので、自宅に上がっているアンテナには採用しています。

トロイダルコア等を用いたバランは、コアの重さや防水の方法に良い解決方法が見いだせなかった為に採用しませんでした。
「理論武装」的な部分はこれくらいにしときます。割と長くなってしまいましたので、製作方法は別ページにすることにします。
ちょっと待ってね・・・。
なお、理論的におかしなところがあるようでしたら、ご教授いただければ幸いです。メールお待ちしております。
 |
| ver.Tenshi使用中。 富士川土手にてお手軽移動。 |
ご意見、ご感想はこちらまで→jg2tsl@jarl.com