「ver.Tenshi」の調整について書いてみます。
ビームアンテナの性能はSWRだけでは決定されません。とは言え、SWRが落ちていなければ実用になりません。ver.Tenshiは2つのSWR最小点を持つことで、結果的に広帯域なアンテナとなっています。Tマッチの動作と合わせて、調整途中で採取したデータを元にいろいろと考察してみたいと思います
なお、測定にはMFJ−259Bを使用しました。この機械はR+|j|が直読できるので大変便利です。ただ、リアクタンス成分が絶対値で、キャパシタンス側なのか、インダクタンス側なのかが計れないのが残念なのですが・・・
調整する点は ・エレメントの長さ ・Tマッチの位置 の2点です。
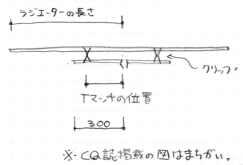
まずは、Tマッチの位置を一定にしたまま、エレメントの長さを少しずつ変えた時のSWRの変化を見てみます。
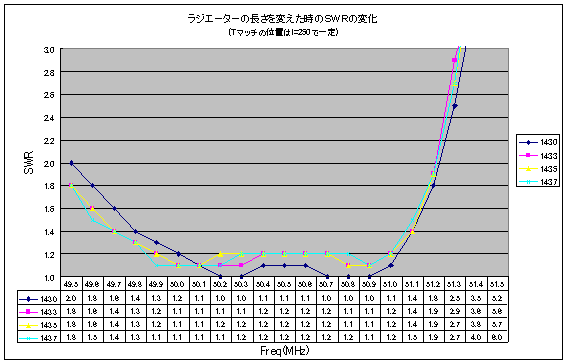
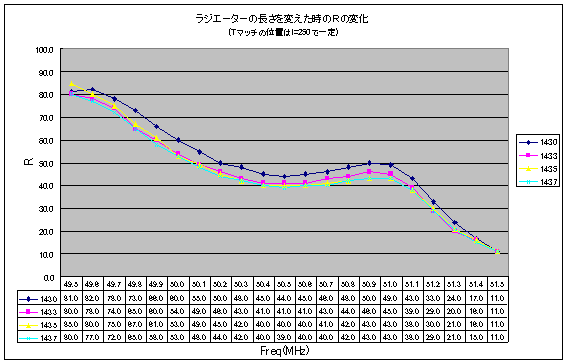
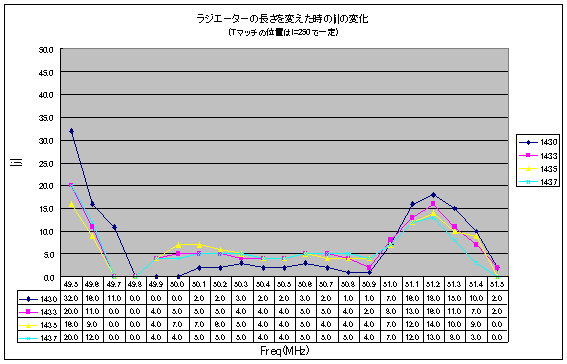
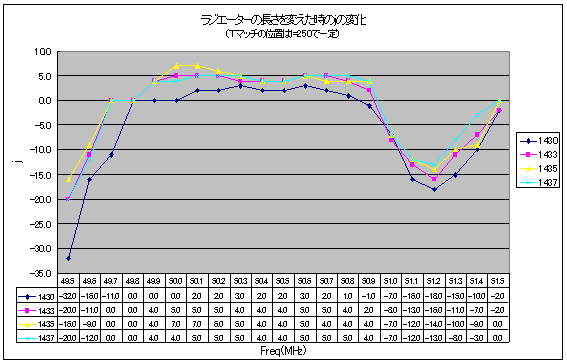
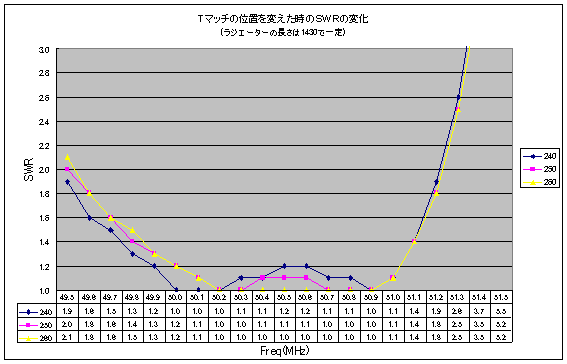
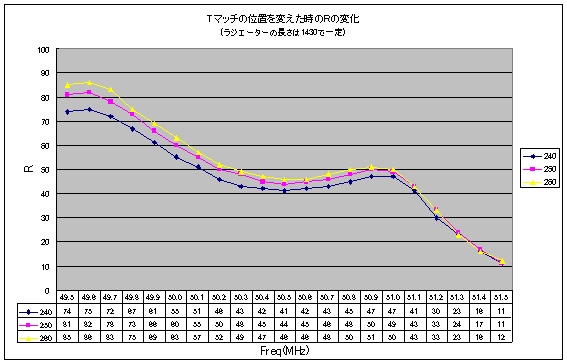
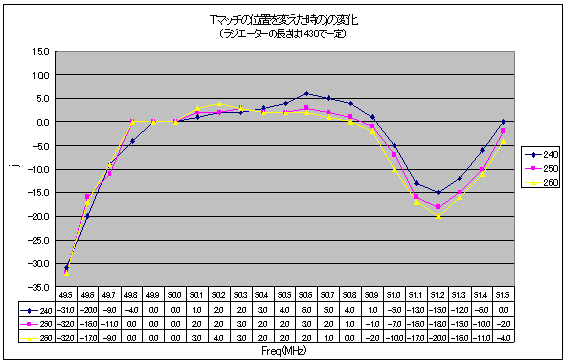
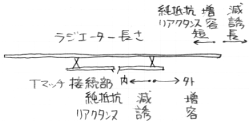
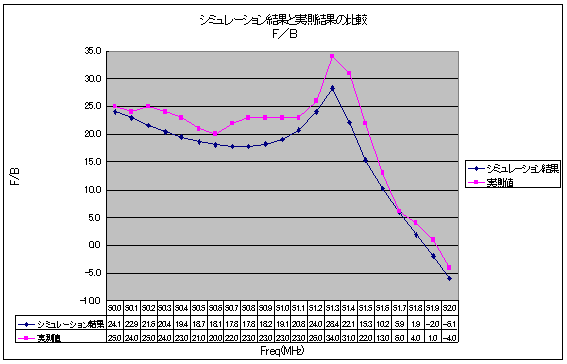
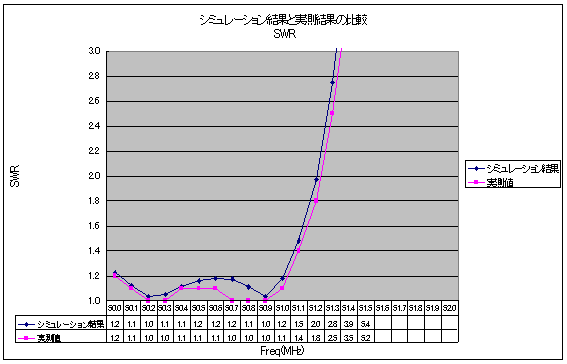
以上、いろいろとグラフにしてみましたが、アンテナの調整で重要なのは、「SWRが落ちているか? どうか?」を見るのではなく、「どこでSWRが落ちているのか?」「どのようなSWRのカーブを描いているのか?」というように細かく現象を観察し、「どのパラメーターを動かすと、どのようにSWRのカーブが変化するか?」をつかんで追いこんでいくということです。そのためにはまめに記録を取る必要があると思います。
根気強く調整してみてください。
調整が済めばアンテナは完成です。
静岡近辺では何人かがこのアンテナを使用していますが、国内コンテストで上位になった人も何人もいますし、DXの迎撃に使用している人もいます。ちょっとした移動運用には最適です。
DXの実績は、CQ誌に掲載された、LU、KL7、H40の他にも、W、PY、CE、5B4等々多くのエンティティーをGETされた方がいます。また、スタックでのDX実績では、9H1、EA(ロングパス)の他に、インド洋スキャッターのSMなんてのもありました。SMなんて自分もQSOしたことがないのに・・・。
サイクルのピークはもう過ぎてしまったかな? でも、50MHzの楽しさはDXだけではありません。このアンテナを製作して移動運用を楽しんでみませんか?
このアンテナを作って、HPに製作記を載せている皆さんのページをリンクしておきます。
JR1ERU
7M2WNR
ご意見、ご感想はこちらまで→jg2tsl@jarl.com